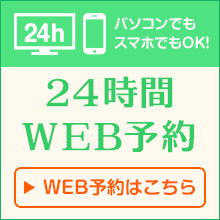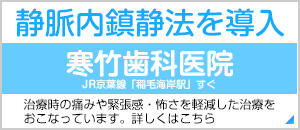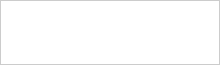こんにちは。君津ピースデンタルクリニックです。
歯科医院で「歯の神経をとる治療をします」や「神経はとらなくて大丈夫ですよ」と言われたことはありませんか。そもそも「歯の神経をとる」とはどういうことなのでしょうか。
今回は、歯の神経をとらなければならない場合や、神経をとった後に気を付けることについてお話しします。
「歯の神経をとる・抜く」とは?
歯の神経とは、「歯髄(しずい)」と呼ばれる組織のことです。歯髄は、歯に水分や栄養、酸素を送り、歯の強さを保つ役割を持っています。
また、むし歯などで歯に異常が起きたときには、痛みを感じさせる働きもあります。進行すると細菌が歯髄に入り込み、強い痛みや頬の腫れを引き起こすことがあります。そのまま放置すると、抜歯になる場合もあります。
「神経をとる・抜く」とは、この歯髄をとり除くことを指し、「根管治療(こんかんちりょう)」とも呼ばれます。
歯の神経をとるのはどんなとき?
では、どのような場合に歯の神経をとる必要があるのでしょうか。
大きなむし歯ができたとき
むし歯が重度になり、激しい痛みなどの症状が出て、通常の治療では治せない場合には、歯の神経をとる治療を行います。
歯が大きく欠けたとき
転んだりスポーツなどで歯が大きく欠けたり、ヒビが入って神経まで達してしまった場合には、神経をとることがあります。
歯周病が進行したとき
歯周病が進んで歯を支える骨がなくなると、根の先から細菌が入り、歯が痛くなることがあります。この場合も神経をとる治療が必要です。
ブリッジ治療などが必要なとき
抜歯が必要な場合、その部分を補う方法の一つに「ブリッジ治療」があります。ブリッジ治療では、失った歯の前後の歯を大きく削るため、治療後にしみたり痛みが出ないよう、あらかじめ神経をとることが多いです。
知覚過敏の症状が治らないとき
知覚過敏とは、むし歯がなくても冷たい水や空気がしみる状態です。通常は薬を塗ったり、知覚過敏用の歯みがき剤で改善しますが、重い場合は神経をとることもあります。
歯の神経をとった場合に気を付けること
神経をとると痛みはなくなりますが、歯に栄養や水分が届かなくなり、歯は「死んだ」状態になります。死んだ歯はだんだん乾燥して、割れやすくなります。もし根の先まで割れたりヒビが入ると、抜歯が必要になることもあります。また、神経をとると痛みを感じなくなるため、むし歯になっても気付かず、かなり進行してしまうことが多いです。定期的に歯科検診を受けて、むし歯ができていないかチェックしましょう。
まとめ
歯の神経をとることで痛みはなくなりますが、歯を失うリスクが高くなります。
また、神経をとった歯の治療は最後まで受け、治療後も定期的に歯科検診を受けましょう。
当院では、治療後の定期検診や、クリーニングなど、お口の中のトラブル予防も行なっています。気になる方はお気軽にご相談ください。